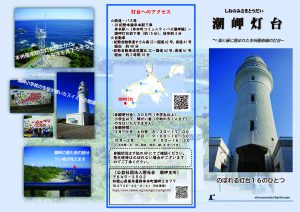紀伊半島南端で、本州最南端に位置する潮岬は、断崖の高さ、50メートル、太平洋に突き出た岬です。 潮岬を形づくる「陸繋島」が細くびれて、串本町とつながっております。
紀伊半島南端で、本州最南端に位置する潮岬は、断崖の高さ、50メートル、太平洋に突き出た岬です。 潮岬を形づくる「陸繋島」が細くびれて、串本町とつながっております。
潮岬灯台は、第一等反射器18個、光源石油灯の不動白光、光達距離19海里の本灯を明治6年9月15日に正式点灯されましたが、 この時の灯塔は、八角形の木造で、我が国最初の洋式木造灯台とされています。その3年前の明治3年6月10日に仮点灯しています。 明治11年に石造りに改造され、大正4年第二等フレネル不動レンズに交換、石油蒸発白熱灯の灯器に改められ昭和3年に電化され、 昭和32年に90センチの回転式に変更、令和5年にはLRL-I2型に変更され、今日に至っております。 交換した第二等フレネル不動レンズは、本灯台の資料室に保存展示してあります。
灯台の灯火中心が、平均水面上49メートル、地上20メートルの灯塔(建造物の高さ23メートル)に昇れば、眼前はまさに、 果てしのない海のうねりが広がり、水平線は遠く、丸みを帯び、空と一体になっています。潮流は、まるで墨でも流したように、 濃紺が入り混じって流れ、灯台付近の豪壮な断崖美と対照的に、岬の先端近くに広がる広大な芝生の草原は、 かって海軍の望楼が設置されていたことから、望楼の芝と呼ばれる一帯で、壮麗な熊野灘の落日は、印象的。 岬の反対側の小高い出雲埼からの展望は360度に広がり、観光客も大勢訪れます。
光源はLEDを使用し、光度690,000力ンデラ、光達距離19海里(約35km)となっております。
●潮岬灯台リーフレット
潮岬灯台リーフレットをPDFで公開しています。画像をクリックして下さい。
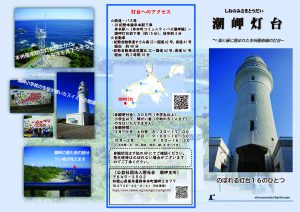
●灯台へのアクセス
☆鉄道・バス等
・JR紀勢本線串本駅下車
串本駅~(串本町コミュニティバス潮岬線)~潮岬灯台前下車(約15分)、徒歩約3分
☆自動車
・紀勢自動車道すさみ南IC~国道42号、県道41号経由 約40分
・紀勢自動車道尾鷲北IC~国道42号、県道41号経由 約2時間10分






 紀伊半島南端で、本州最南端に位置する潮岬は、断崖の高さ、50メートル、太平洋に突き出た岬です。 潮岬を形づくる「陸繋島」が細くびれて、串本町とつながっております。
紀伊半島南端で、本州最南端に位置する潮岬は、断崖の高さ、50メートル、太平洋に突き出た岬です。 潮岬を形づくる「陸繋島」が細くびれて、串本町とつながっております。